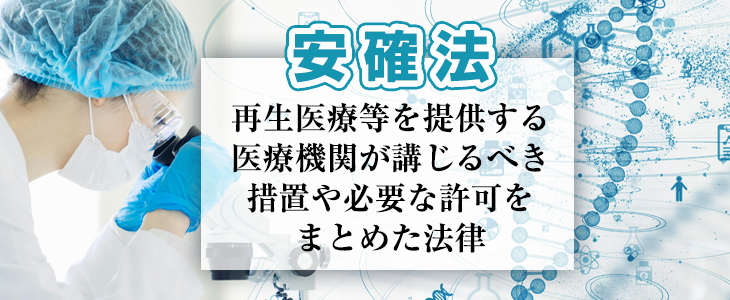新着情報
安確法とは?2024年の改正内容や施行規則・薬機法との違いを解説
近年、iPS細胞やES細胞などを用いた再生医療が注目される一方、安全性や有効性を適切に確保するための制度整備が求められてきました。こうした背景のもとに制定されたのが「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(安確法)」です。
この記事では、安確法と薬機法の位置づけや、2024年の改正内容などを解説します。再生医療に携わる医療機関がどのような制度上の取り組みを行うべきかについて、ポイントを整理しながら伝えるため、ぜひ参考にしてください。
1. 安確法(再生医療等の安全性の確保等に関する法律)とは
安確法とは、再生医療等を提供する医療機関が講じるべき措置を明確化するとともに、特定細胞加工物の製造にかかわる許可等の制度を定めた法律です。
なお、安確法における特定細胞加工物とは、再生医療等で使用される細胞加工物の中でも再生医療等製品以外のものを指します。
第一条
この法律は、再生医療等に用いられる再生医療等技術の安全性の確保及び生命倫理への配慮(以下「安全性の確保等」という。)に関する措置その他の再生医療等を提供しようとする者が講ずべき措置を明らかにするとともに、特定細胞加工物の製造の許可等の制度を定めること等により、再生医療等の迅速かつ安全な提供及び普及の促進を図り、もって医療の質及び保健衛生の向上に寄与することを目的とする。
引用:e-gov法令検索「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」引用日2024/2/9
安確法の正式名称は「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」で、「再生医療等安全性確保法」と呼ばれることもあります。
再生医療にかかわる医療機関や細胞の培養・加工を行う施設の基準を示し、再生医療の安全性確保や普及促進を図ることが、安確法の目的です。
1-1. 薬機法と安確法の違い・関係性
安確法に関連する法律には薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)があります。
薬機法とは、医薬品・医療機器等の品質や安全性を確保することを目的とした法律です。薬機法は細胞治療と遺伝子治療用製品を「再生医療等製品」というカテゴリで定義していて、再生医療等製品の有効性・安全性の確保と、製造所の基準を規定しています。
また、薬機法では再生医療等製品の「条件及び期限付き承認制度」があることが特徴です。条件及び期限付き承認制度は治験後に条件・期限付きの承認が受けられる仕組みで、再生医療等製品の研究開発や普及推進がしやすくなっています。
薬機法と安確法はどちらも再生医療関連の法律であるものの、対象とする範囲に違いがあります。薬機法は企業が再生医療等製品を製造する場合にかかわる法律であり、対して安確法は医療機関が再生医療等を提供する場合のルールを定めた法律です。
1-2. 安確法が制定された背景
安確法が制定された背景には、再生医療技術の急速な発展に対し、日本国内の再生医療にかかわる法制度が整備不足であったことが挙げられます。
安確法の制定以前は、再生医療等臨床研究は国への手続きが必要であり、厚生労働省による審査に数か月を要していました。
一方、医療機関で行われる自由診療の再生医療は国への手続きが行われていませんでした。再生医療の有効性や安全性が評価されないまま施術が行われる状態が続き、結果としてさまざまな医療事故が発生しています。
以上の経緯により、国は再生医療の安全性を確保するために、医療機関と細胞の培養・加工を行う施設について基準を設ける安確法を制定しました。
2. 安確法の施行規則
安確法には以下で紹介するような施行規則があります。
再生医療等を提供する組織や、特定細胞加工物製造を行う施設は、安確法の施行規則に則って手続きや基準の遵守をしましょう。
2-1. リスクに応じて再生医療等の提供手続きが必要になる
医療機関が再生医療等を提供するときは、実施する再生医療等のリスクに応じて提供手続きを行わなければなりません。
再生医療等は「第1種」「第2種」「第3種」の3分類があり、下記のように生命や健康に対するリスクに応じて分けられています。
| 分類 | 説明 | 主な再生医療等の例 |
|---|---|---|
| 第1種再生医療等 | ヒトに未実施など高リスクのもの | ES細胞やiPS細胞を使用する医療など |
| 第2種再生医療等 | ヒトに実施中であり中リスクのもの | 患者自身の体性幹細胞を使用する医療など |
| 第3種再生医療等 | リスクが低いもの | 体細胞を加工する医療など |
出典:厚生労働省「再生医療等の安全性の 確保等に関する法律について」
いずれの分類においても提供手続きは、医療機関の申請した再生医療等提供計画について審査が行われた後に、厚生労働大臣に提供計画を提出するという流れです。
しかし、第1種再生医療等と第2種再生医療等は「特定認定再生医療等委員会」が審査を行い、第3種再生医療等は「認定再生医療等委員会」が審査を行う点が異なります。
また、第1種再生医療等では厚生労働大臣に提供計画を提出した日から90日間の提供制限期間が定められています。提供制限期間中は厚生労働大臣が計画の変更命令を行うケースがあり、他の2種類よりも提供手続きが厳格であることが特徴です。
2-2. 細胞培養加工の外部委託に基準が設けられる
医療機関が提供する再生医療等において、細胞の培養や加工を外部委託する場合は、外部委託の施設に基準が設けられています。
細胞培養加工施設が遵守しなければならない基準は、「構造設備基準」と「製造管理・品質管理等の基準」の2つです。
- 構造設備基準
細胞培養加工施設の構造設備は、厚生労働省令が定める基準に適合していなければなりません。
構造設備基準は主に下記の項目があり、各項目で備えるべき設備の内容が定められています。
- 細胞培養加工施設の構造
- 作業所
- 作業室または作業管理区域
- 清浄度管理区域
- 無菌操作等区域
- 貯蔵設備
- 試験検査
- 製造管理・品質管理等の基準
特定細胞加工物の製造事業者は、厚生労働省令が定める製造管理・品質管理等の基準を遵守しなければなりません。
厚生労働省令が定める製造管理・品質管理等の基準は、施設管理者の業務や職員の配置、特定細胞加工物標準書や手順書等の作成、品質管理など多岐の項目にわたります。
2-3. 再生医療等提供基準の遵守が求められる
再生医療等を提供する医療機関は、厚生労働省令が定める再生医療等提供基準を遵守しなければなりません。
再生医療等提供基準は多岐の項目があり、主な例としては下記の内容が挙げられます。
- 再生医療等を提供する医療機関が有する人材の配置や資質
- 再生医療等を提供する医療機関の構造設備
- 細胞の入手方法
- 個人情報の取り扱い
- 健康被害の補償についての必要な措置
など
また、再生医療等提供基準には含まれていないものの、再生医療等を提供する医療機関に求められる事項もあります。
再生医療等を提供する医療機関は、再生医療等提供基準を遵守するとともに、求められる事項も満たすことが大切です。
3. 安確法改正の2024年改正概要
安確法は近年の技術革新等を踏まえた見直しが行われ、2024年6月に改正された安確法が施行されました。
改正された安確法で見直しが行われたポイントは、下記の2つです。
・安確法の見直し内容(2024年)
- 細胞加工物を用いない遺伝子治療等に対する再生医療等安全性確保法の適用
改正後の安確法では、細胞加工物を用いない遺伝子治療等についても規制を適用できるように変わっています。
細胞加工物を用いない遺伝子治療等とは、遺伝子そのものを人体に投与したり、体内での遺伝子改変を行ったりする治療法のことです。
改正前の安確法が施行された当時、細胞加工物を用いない遺伝子治療技術は広く行われていませんでした。
しかし、近年は遺伝子治療にかかわる技術が発展し、細胞加工物を用いない遺伝子治療等の将来的な普及が予測されています。細胞加工物を用いない遺伝子治療等の安全性を確保するとともに、普及促進を目的として、安確法の適用範囲を広げる改正が行われました。
- 認定再生医療等委員会に対する立入検査等の規定の整備
再生医療等の提供手続きにかかわる認定再生医療等委員会について、立入検査や欠格事由の規定が整備されるように法改正が行われています。
認定再生医療等委員会は再生医療等の提供手続きにおいて、医療機関が作成した提供計画を審査する役割を担っています。
しかし、認定再生医療等委員会が実施する審査は時間や質にばらつきがあり、一定の安全性を確保できていない課題がありました。
安確法の改正によって認定再生医療等委員会に対する立入検査等の規定が整備されたことで、審査の時間や質の一定程度の均一化が期待されています。
安確法は比較的新しい法律であり、法規定の範囲である再生医療分野は顕著な技術革新が見られます。
今後も安確法が改正される可能性はあるため、再生医療を提供する医療機関などの関係者は法改正に対応できるよう、安確法の最新情報を常に収集する必要があるでしょう。
まとめ
安確法は、再生医療を行う医療機関や細胞培養加工施設の基準を明確化し、安全面を重視した実施体制を築くことを目的としています。そのため、リスク分類に応じた審査や、外部委託先の構造設備基準の遵守など、具体的な手続きや要求事項が細かく定められています。さらに2024年改正では、細胞加工物を用いない遺伝子治療も規制対象に含めるなど、最新の技術動向を見据えた対応が行われました。
再生医療において、安確法は患者への治療の安全性と信頼性を向上するために必要です。細胞を収容・保存・輸送するための容器の品質も再生医療に関わる1つとして適切に管理される対象です。
iP-TEC®では、現在特注対応の容器を提供する一環で、無菌性確保のための滅菌加工や生体適合性、その他試験を行い、トレサビリティや容器の品質管理に関わる書面も特注容器のご依頼をいただいたクライアントと協議の上、作成を行っております。iP-TEC®で対応可能かなどご興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。