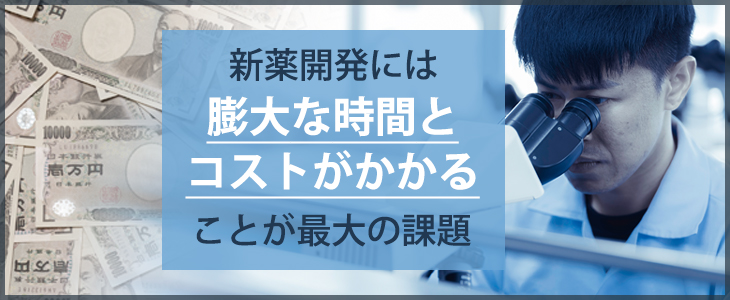新着情報
MPSで創薬プロセスはどう効率化されるのか?
創薬には膨大な時間と費用がかかり、前臨床から臨床試験に至るまでに多くのリスクが伴います。従来の動物実験や2次元培養では、ヒトにおける反応の再現性に限界があり、新薬の開発成功率にも大きな影響を与えていると考えられています。こうした課題を背景に注目されているのが、MPS(Microphysiological Systems/生体模倣システム)です。
MPSは、ヒトの臓器構造や機能をマイクロチップ上で再現し、薬剤の有効性や毒性を高精度に評価できる技術です。当記事では、MPSの概要から創薬への貢献、コスト削減効果、そして今後の展望までを詳しく解説します。
1. 生体模倣システム「MPS」と創薬のつながり
MPSは、ヒトの臓器機能を再現することで、創薬初期から高精度な評価を可能にし、効率的な新薬開発を支える技術です。ここからは、MPSと創薬の関係について説明します。
1-1. MPSとは
MPS(Microphysiological Systems)とは、生体組織や臓器の微細な構造や機能、さらには体液循環などの環境を模倣した、マイクロスケールの評価システムです。チップ上に構築された臓器モデルや細胞構造により、ヒトの生理的反応を再現でき、薬物の有効性や毒性を高い精度で評価することが可能となります。
従来の動物実験や2次元細胞培養では、ヒト特有の反応を正確に再現するには限界がありました。MPSは、こうした課題を克服する次世代技術として注目されており、創薬分野における評価の高精度化と効率化を支える鍵と位置づけられています。
また、単一の臓器にとどまらず、複数の臓器を連結させることで、より実際の体内環境に近い挙動の再現が可能です。そのため、創薬に加えて、先端医療、毒性試験、疾患研究といった幅広い分野での応用が期待されています。
1-2. 従来の創薬プロセスとその課題
創薬には、平均して10〜15年という長い期間と、数百億円規模の膨大な開発費用がかかるとされています。その背景には、創薬プロセスが極めて複雑であり、各段階に多くの不確実性が存在するという構造的な問題があります。特に、前臨床試験で得られた結果がヒトにおいて再現されないという点が、大きな課題となっています。
1-2-1. 創薬プロセスの全体像
創薬は、以下の6つのプロセスに分けられます。
| 1 | 標的探索 |
|---|---|
| 病気に関与する分子や遺伝子を特定する | |
| 2 | ヒット化合物の同定 |
| 数万〜数百万の化合物からスクリーニングで候補物質を選抜する | |
| 3 | リード最適化 |
| 候補化合物の構造を改良し、有効性や安全性を高める | |
| 4 | 前臨床試験(in vitro/in vivo) |
| 細胞や動物を用いて有効性や毒性を評価する | |
| 5 | 臨床試験(Phase I~III) |
| ヒトにおける安全性・有効性を確認する | |
| 6 | 承認・製造・販売 |
| 薬事承認を経て市場に投入する | |
このうち、前臨床から臨床試験へと進む段階は「開発の関門」とも呼ばれ、予測不能なリスクが最も多く潜んでいるフェーズです。
1-2-2. 主な課題
従来の創薬プロセスには、以下のような構造的な課題があります。
- 動物実験とヒトとのギャップ
動物とヒトでは代謝や生理機能が異なるため、動物で安全とされた薬剤がヒトで副作用を引き起こす例もあります。特に肝臓、心臓、神経に関する毒性は、ヒト特有の反応として後から判明することも少なくありません。 - 臨床試験での高い失敗率
有効性を検証するフェーズIIおよび大規模試験のフェーズIIIでは、全体の70〜80%が失敗に終わるとされています。これは、前臨床試験での予測精度の低さや、ヒトの個体差の大きさが主な原因です。 - 高コスト・長期間
新薬開発には平均で13年もの年月が必要であり、その過程で開発中止や後戻りが発生すれば、投入したリソースが大きく無駄になります。こうしたコスト増加は、最終的に医薬品価格にも反映されることになります。 - 個別化医療への対応困難
従来の手法は「平均的な患者像」を前提として設計されており、がんや希少疾患のような個人差の大きい疾患に対応するのは難しいのが現状です。今後は、個々の患者の反応を正確に把握し、個別に最適な治療を提供する評価技術が求められます。 - 倫理的・社会的課題
動物実験の削減は世界的な潮流であり、欧州を中心に、一部の化学物質に関しては動物試験がすでに禁止されています。3Rs(Replacement, Reduction, Refinement)の理念のもと、動物実験に代わる新しい手法の開発と導入が求められています。
1-2-3. なぜMPSが求められるのか
前述のような課題を背景に、ヒトの体内環境を再現できるMPSが注目を集めています。MPSを活用することで、前臨床の段階からヒトに近い反応を観察することが可能となり、開発初期の段階で「失敗しやすい薬剤」を見極めることができます。
このような早期の見極めにより、開発期間の短縮やコスト削減につながるだけでなく、患者ごとに異なる副作用のリスクを予測する新たなアプローチとしても期待されています。創薬の精度とスピード、さらに倫理性を同時に高められる技術として、MPSはまさに次世代の創薬を支える鍵となる存在と言えるでしょう。
2. MPSがもたらす創薬プロセスの効率化
MPSは、創薬の前臨床試験において判断精度を大幅に向上させる技術として注目されています。従来の動物実験や2次元培養では再現が難しかったヒトの生理的応答を、より高精度に模倣できるため、創薬プロセス全体の効率化に大きく寄与します。
特に、スクリーニング段階での判別精度の向上、有害事象の予測、そして臓器間相互作用の可視化といった点で、その効果が顕著に現れています。
2-1. 前臨床段階での高精度なスクリーニング
MPSでは、ヒト由来の細胞やiPS細胞を用いて、臓器の三次元的な構造や機能を再現したモデルを構築します。こうしたモデルを活用することで、候補化合物がヒトの体内でどのような反応を引き起こすかを、より生理学的に近い形で予測することが可能です。
その結果、薬効が期待できない化合物を創薬初期の段階で効率的に除外でき、有望な候補物質に対して資源や時間を集中的に投入することができます。
2-2. 有害事象の予測精度向上
従来の動物実験では、ヒト特有の毒性を見逃してしまうリスクが常に伴います。また、2次元細胞培養では、臓器本来の機能や細胞間の相互作用を十分に再現できず、毒性評価の精度に限界がありました。
MPSは、肝臓や心臓などヒトの臓器に近い環境をチップ上で再現することで、薬剤による毒性をより正確に検出することが可能です。さらに、患者由来のiPS細胞を用いたMPSでは、個人ごとの副作用リスクの予測も可能となっており、個別化医療への応用が期待されています。
2-3. 臓器間相互作用の可視化
ヒトの体内では、薬剤は複数の臓器を通過しながら吸収・代謝・排泄されます。しかし、従来の評価系ではこうした臓器間の相互作用を再現することが難しく、二次的な毒性や予測外の反応を見落とすリスクがありました。
MPSでは、複数の臓器モデルを連結し、血流を模した微小循環環境を構築することで、薬剤が体内を移動するプロセスや代謝物が次の臓器に及ぼす影響などを詳細に観察できます。このように、MPSは単一臓器での評価にとどまらず、より包括的に薬物動態を把握できる手段として、創薬における精度の高い解析を可能にしています。
3. コスト・期間の削減効果
新薬開発における最大の課題の1つが、「膨大な時間とコスト」とされています。その背景には、各段階での失敗リスクの高さや、非効率な試験プロセスが深く関係しています。
MPSの導入は、こうした創薬プロセスの構造的な課題を抜本的に見直し、全体の最適化を促進する革新的な技術として注目されています。
3-1. なぜコストと期間がかかるのか?
創薬には、膨大な資金と長い年月が必要とされます。その要因の1つが、各段階に存在する「不確実性」と「非効率性」です。以下に、創薬の各ステージに存在する異なるコスト要因とリスクを示します。
| 前臨床試驗 | 臨床試験 (フェーズⅠ~Ⅲ) | 製造開発 (商品化準備) | |
|---|---|---|---|
| 主なコスト要因 |
|
|
|
| リスク |
|
|
|
このように、創薬はリスクとコストが累積していく構造になっており、「いかに早期に見込みのない候補を見極めるか」が重要な課題となっています。MPSは、その判断を前倒しで可能にし、リスクの早期の可視化・回避を実現する役割を担っています。
3-2. MPSがどう効率化するのか?
MPSは、従来の創薬プロセスにおける無駄やリスクを抑え、開発全体を効率化する技術として期待されています。以下では、具体的な効率化のポイントを4つに分けて解説します。
3-2-1. 前臨床試験の短縮と失敗回避
MPSは、ヒトに近い臓器環境を模倣することで、薬剤の有効性や毒性をより正確に初期段階から評価できます。そのため、臨床試験に進む前に「効果が不十分」あるいは「副作用リスクが高い」化合物を早期に除外でき、無駄なリソース投入を避けることが可能です。結果として、試験全体の期間が短縮され、成功率も向上します。
3-2-2. 臨床試験の成功率向上
MPSによって得られる高精度なデータは、治験設計の精度向上にもつながります。従来は動物実験や2次元細胞培養に依存していたため、臨床段階で予測外の副作用や効果不足が発生することも多くありました。しかし、MPSを活用すれば、よりヒトに近い反応を事前に把握できるため、フェーズIIやIIIといった高コストな臨床試験での中止リスクを大幅に低減できます。
3-2-3. 動物実験の削減によるコストダウンと倫理面の改善
MPSは、動物実験の代替技術としても期待されています。動物の飼育や管理にかかるコストを削減できるだけでなく、国際的な倫理基準にも対応しやすくなります。規制に準拠したデータ取得の負担も軽減されます。欧州を中心に動物試験の削減が進む中、MPSは企業が社会的責任を果たしつつ、経済的メリットも享受できる方法となっています。
3-2-4. 試験の並行化・自動化に対応
MPSは小型のデバイス内で複数の臓器モデルや条件設定を並行して扱えるため、試験の高速化が可能です。さらに、ロボットシステムや自動化装置と組み合わせることで、多数の検体を同時に処理し、短時間で信頼性の高いデータを取得できるため、創薬スピードが格段に向上します。将来的には、MPSを中心とした自動評価プラットフォームの開発が進むことも予想されています。
これらの多面的な効率化によって、MPSは従来の創薬工程の各フェーズにおいて大幅な期間短縮をもたらすと期待されています。以下は、従来の創薬工程とMPS導入による短縮見込み、ならびに各工程における主な効果をまとめた表です。
| 工程 | 従来の 期間 | MPS導入後の 短縮見込み | 主な効果 |
|---|---|---|---|
| ターゲット探索 | 1~2年 | 短縮効果なし | – |
| リード化合物探索 | 2~3年 | 0.5~1年短縮 | スクリーニング精度の向上 |
| リード最適化 | 1~2年 | 0.5年短縮 | 効果・毒性評価の効率化 |
| 前臨床試驗 | 2~3年 | 1~2年短縮 | 動物実験の補完・代替 |
| 臨床試験 (フェーズⅠ~Ⅲ) | 5~7年 | 1~3年短縮 | 臨床試験成功率の向上 |
| 合計 | 10~15年 | 3~5年短縮 | 全体の期間を 30~40%短縮可能 |
MPSを導入することには、特に前臨床試験と臨床試験段階での期間短縮効果が大きく、全体の創薬プロセスを3〜5年短縮する可能性があります。効率化だけでなく、創薬の成功率を高める効果も期待されており、製薬業界における革新技術として今後の普及が進むと考えられています。
4. 今後の展望
生体模倣システム(MPS)は、創薬における精度と効率の向上にとどまらず、医療や生命科学研究のあり方そのものを変革する可能性を秘めています。現在は主に前臨床試験での評価ツールとして導入が進められていますが、今後はさらに幅広い分野への応用が見込まれ、国際的な制度設計との連携も期待されています。
4-1. 創薬への本格実装
一部の製薬企業では、すでに研究開発部門においてMPSの導入が開始されています。今後は、前臨床試験における主要な評価手法として定着すると考えられています。特に注目されているのが、複数の臓器モデルを連結する「マルチオルガンMPS」です。
マルチオルガンMPSは、薬物が体内を移動する過程をリアルに再現できる仕組みであり、「人間オンチップ」とも呼ばれるような統合型評価システムの実現が視野に入っています。このような技術が確立されれば、従来の創薬における「動物実験から臨床試験への大きな飛躍」をスムーズにつなぐ手段となる可能性があります。
4-2. 個別化医療への応用
MPSのもう1つの大きな可能性は、個別化医療(Precision Medicine)への応用です。iPS細胞技術と組み合わせることで、患者一人ひとりの細胞から臓器モデルを構築し、その人に最適な薬剤を評価できるようになります。
がんや希少疾患、遺伝性疾患など、個人差が大きく治療が難しい病態に対しても、精密かつ的確な薬剤選定が可能となるでしょう。MPSは、個別化医療の実現に欠かせないプラットフォームになると考えられています。
4-3. 再生医療・疾患モデルへの展開
MPSは創薬だけでなく、疾患の病態を再現する研究ツールとしての利用も広がっています。がんやアルツハイマー病、自己免疫疾患など、従来のモデルでは再現が困難だった病態についても、MPSなら精密なシミュレーションが可能です。
さらに、オルガノイドやAIによる解析技術と組み合わせることで、MPSは「次世代バイオモデル」として再生医療や臓器機能の代替技術にも波及効果をもたらしています。特定の疾患に対して、よりリアルなヒト疾患モデルを構築することによって、病態の進行や薬剤応答の定量的な観察を可能としています。
4-4. グローバル連携・標準化の加速
MPSの普及には、国際的な規制機関との連携が不可欠です。米国FDA(食品医薬品局)や欧州EMA(医薬品庁)では、MPSを含む新たな評価技術に関する基準整備が進められています。将来的には、MPSを用いたデータが医薬品承認における正式なエビデンスとして認められる可能性も高まっています。
日本においても、こうした国際的動向に追随すべく、制度設計や規制基準の整備が急がれています。さらにグローバルな標準化が進めば、国を超えたデータ共有や多国籍治験の効率化も実現しやすくなるでしょう。
まとめ
MPS(生体模倣システム)は、創薬分野における高精度かつ高効率な評価手法としての活用にとどまらず、個別化医療や再生医療、さらには国際的な制度整備の進展といった、社会全体の変化を牽引する可能性を持つ技術です。今後、MPSの研究開発と社会実装がどこまで進むのかに、世界中の医療関係者や研究者からの注目が集まっています。
iP-TECでは、MPSの発展と創薬分野へのさらなる貢献を目指し、多連灌流用の「マイクロチューブポンプシステム」、初期流量条件検討用の「灌流トライアルポンプキット」、携帯に便利な「(仮称)ポケットタイプ灌流ポンプキット」など、新たな灌流培養装置の開発に取り組んでおります。また、MPSに関する学会やコンソーシアムに積極的に参加し、容器デバイス開発に生かしております。